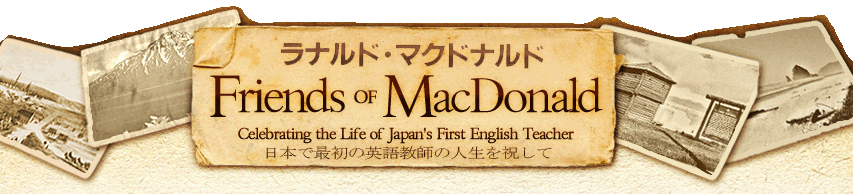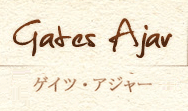文・写真:谷口雅春 / 2010年11月1日
なんと途方もない聞き書き本が僕たちにもたらされたことだろう。
前稿で露口啓二が紹介したように、このたび利尻町立博物館学芸課長の西谷榮治さんが著した「利尻の語り」は、1986年から23年もの長きにわたって北海 道利尻町の広報誌「広報りしり」に連載されてきた、島民やゆかりの人々の聞き書きを再編集したもの。B5版464ページの大部に、146人の語りと、内容 にちなむ写真がおさめられている(編集者西村淑子さんの丹念な仕事が偲ばれる)。
例えば伊勢から渡った海女たちの暮らし。ニシンの爆発的な大漁や、クジラが浜に寄り付 いた挿話。樺太との深い関わり。集落ごとの祭りや演芸会、相撲大会に血肉を踊らせた青年団の活動。盆や節句、あるいは学び舎の行事の数々。各地からの開拓 移住のあらましに、襞のように入り組んだ地名や地誌の言い伝え…。明治、大正、昭和にまたがるおびただしい主題が、欄外の注釈が欠かせないような独特の言 い回しで展開されていく。話し言葉をていねいになぞる筆致も魅力だ。
利尻に本格的に和人が移り住んだのは安政年間(1854〜1860)のことだという。 その前史として17世紀後半にはすでに松前藩の場所経営があり、時代を下れば今号のカイでもふれた、津軽や秋田藩士たちによるロシアへの備えがあった。北 海道本島と共通する水産資源と地政学的意味によって、利尻島の近代は急駆動される。内地とは比較にならない厳しく複雑な気候をまとった利尻山 (1721m)が海底から一気にそびえ、ごく限られた土地と海で繰り広げられてきた濃密な歴史は、この島の輪郭に北海道史の縮図や、「もしも世界が100 人の村だったら」といった思考モデルを誘うかもしれない。しかしそんな紋切り型のまなざしは、語りのディテールの強度の前に恥じ入るばかりだろう。本書に 満ちているのは、郷愁の下味がついた北方イメージの断片などではなく、記(しる)されることもなくひっそりと記憶に眠っていた、ひとりひとりの固有の身体 から編み上げた利尻島の風土であり、なまなましい人生そのものなのだ。
カイにも、まだ9回にすぎないが井上由美が連載している聞き書きシリーズ、「北海道の 物語」がある。聞き書きにおいて話し言葉から書き言葉への変換は、書き手をつねに正解のない問題の前に立ち止まらせる。本書からもその困難との折り合いの 軌跡が浮かび上がるが、464ページというボリュームは、口語と記述をめぐる日本語の成り立ちまでも意識させるだろう。読み進みながら想起したのは、水村 美苗の「日本語が亡びるとき」(筑摩書房.2008)だ。水村は、19世紀に「西洋の衝撃」を受けた日本の知識層が、その現実を語るために日本語の古層を 掘り返し、日本語のあらゆる可能性をさぐりながら「出版語」を作りだしたこと(その言葉によって日本の近代文学は立ち上がった)。言文一致とは、単に口語 を書き言葉に移した取り組みではなく、幕末から明治の東アジアの激動の中で考案され磨かれてきた壮大なプロジェクトだったこと。そうした史実に無頓着なま ま、緊張感をなくした日本語はインターネットの時代に英語に飲み込まれようとしていることをスリリングに論考する。同次元で「利尻の語り」には、亡びゆく 土地の記憶をなんとかつなぎ止めようとする、現代日本語の格闘が浮かび上がっているともいえる。
マネーやイメージは根を持たないが、人間は土地を離れて生きることができない。20年 以上の歳月をかけ、これからもなお続く聞き書きは、利尻で生まれ育ち東京で学び、利尻に根ざし続けることを選んだ西谷さんにしかできない仕事だろう。受け 止める僕たちは、亡びるものへの感傷などで視界を汚してしまう前に、語りのリアルな細部から、北海道がほんとうに守るべきものや受け継ぐべき価値をしっか りとまさぐっていきたい。

(自費出版。3,360円で実費発売。問い合わせは利尻町立博物館 tel:0163・85・1411へ)